関連情報
- 関連法案 -
循環型社会を形成
「10年度にごみ処分量半減」
リサイクル促進とごみの発生抑制を目指す、国の2010年度までの循環型社会形成推進基本計画案が22日、明らかになった。
10年度のごみ処分量を2000年度の約半分の2700万トンとし、国民と企業の意識改善目標も定めている。
27日の中央環境審議会に提出、3月末までに閣議決定し、2003年度から実施する。
循環型社会形成推進基本法に基づく初の計画で、5年後に見直す予定だ。
計画案は大量生産と大量消費の社会は持続不可能とし、資源を循環させ自然と共生する社会を提案。
四季を感じながら生きるスローライフが受け入れられ、生ごみの堆肥利用などが進むとイメージを示した。
10年度の具体的数値目標として、リサイクル推進と資源消費量の抑制で、廃棄物の最終処分量を2000年度(5600万トン)の約半分の2700万トンと設定。
国民一人ひとりの意識改善が不可欠とし、ごみの減量化やリサイクルを心がけている人の割合を90%(01年の内閣府調査で71%)、環境保全活動に参加した人の割合を50%(02年の環境省調査で20%)にすることを目指すとした。
企業に対しても環境対策と成果を会計的に示す環境会計の積極導入を呼び掛けることにした。
| 2000年 | 2010年 | ||
| 資源生産性(1トン当り) | 28万円 | 39万円 | |
| 循環利用率 | 10% | 14% | |
| 最終処分量 | 5600万トン | 2700万トン | |
| 国民 | ゴミの減量化を心がけている | 71% | 90% |
| グリーン購入している | 83%(01年7月) | 90% | |
| 環境保全活動に参加した | 20%(02年2-3月) | 50% | |
| 上場企業 | グリーン購入実施 | 15%(01年度) | 50% |
| 環境会計実施 | 23%(01年度) | 50% | |
多孔質で微生物の繁殖に好都合
毎日のようにゴミ回収車が忙しく走り回る時代である。
何とかゴミを少なくしたい、そんな考えから生まれたのが生ゴミ分解装置だろう。
この装置で生ゴミを分解し、減量する主役は微生物だが、その微生物を繁殖させるのに、おがくずや木材チップは有効である。
金属やプラスチックと違って、おがくずや木材チップは多孔質であるために、湿度を適度に保ち、逆に水はけも良く過度に湿らず、通気性もよいので、空気との接触で繁殖する妖気性バクテリアなどの微生物にとって、繁殖に好都合な場所となる。
微生物は生ゴミを栄養源として分解し、最終的には二酸化炭素と水にする。
実際には装置の中に、おがくずと生ゴミを入れ、分解を早めるために好気性微生物を入れ、空気との接触を多くするために自動撹拝するといった操作をする。微生物を加えずに、生ゴミ中の微生物を利用することもある。
おがくずを利用した生ゴミ分解装置では悪臭が発生せず、生ゴミに含まれていたカリ、リン、窒素などが、おがくずに含まれるようになるので、生ゴミ処理後の、おがくずは、肥料や土壌改良材として有効であり、また、キノコ栽培用の培地としての利用も可能である。
おがくずよりも、サイズの大きい木材チップを使用した例も報告されている。
この場合には、生ゴミ処理によってチップの大きさが小さくなるものの、おがくず同様、ミネラル類の濃度の増加がみられる。
チップの場合には、おがくずのように細かくないので、たい肥化は難しいようだが、その形状を利用して、ボードなどへの利用可能性も検討されている。
生ゴミ処理中に微生物の働きで、固かったチップが軟らかくなっているので、蒸気をあてて軟らかくする工程が省略でき、生ゴミ処理チップのままで、加熱、圧密化処理することで接着剤なしにボード製造が可能であるという。
処理チップでは、微生物によって物理的な劣化も起こっているために、比較的低いエネルギーで粉体化が可能であり、たい肥やキノコ培地としての利用も可能である。
生ゴミ分解装置による生ゴミ分解は、微生物という自然の力と、おがくずなどの廃材を効率よく利用した環境にやさしい処理法といえよう。
(東京大学大学院農学生命科学研究科教授・谷田貝光克)
循環型社会形成推進基本法の概要
1.「循環型社会」とは、
ア. 廃棄物等の発生抑制
イ. 循環資源の循環的な利用及び
ウ. 適正な処分が確保されること天然資源の消費を抑制し、
環境への負荷が出来る限り低減される社会
2.法の対象となる破棄物のうち有用なものを「循環資源」と定義
3.処理の「優先順位」を初めて法定化
ア. 発生抑制
イ. 再使用
ウ. 再生利用
エ. 熱回収
オ. 適正処分
4.国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化。循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者及び国民全体で取り組んでいくため、これらの主体の債務を明確にする。
ア. 事業者、国民の「排出者責任」を明確化。
イ. 生産者が、自ら生産する製品等について使用され廃棄物になった。
後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を確立。
5.政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定。循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府は「循環型社会形成推進基本計画」を次のような仕組みで策定。
ア. 原案は、中央環境審議会が意見を述べる指針に即して、環境大臣が策定。
イ. 計画の策定に当たっては、中央環境審議会の意見を聴取。
ウ. 計画は、政府一丸となった取り組みを確保するため、関係大臣と協議し、閣議決定により策定。
エ. 計画の閣議決定があったときは、これを国会に報告。
オ. 計画の策定期限、5年ごとの見直しを明記。
カ. 国の他の計画は、循環型社会形成推進基本計画を基本とする。
6.循環型社会の形成のための国の施策を明示
ア. 廃棄物等の発生抑制のための措置。
イ. 「排出責任」の徹底のための規制等の措置。
ウ. 「拡大生産者責任」を踏まえた措置。
(製品等の引き取り・循環的な利用の実施・製品等の関する事前評価)
エ. 再生品使用の促進。
オ. 環境保全上の支障が生じる場合、原因事業者にその現状回復等の費用を負担させる措置。
参 考
本法は2000年5月26日に、成立し6月2日に交付された。
尚今国会で本法律と一体的に整備された法律は、以下のとおり。
〇廃棄物処理関係 〇リサイクル関係
・廃棄物処理法等の改正
・再生資源利用促進法の改正
・建設資材リサイクル法
・食品リサイクル法
・グリーン購入法
参考資料 静岡県農林水産部みかん市場室 2013年2月16日
生ゴミは腐敗しやすく悪臭も放ちやすいので、輸送や集積が難しい。
しかも発生源が分散している。当然、各発生源での個別処理が望ましい。
ディスポーザーを用いて生ゴミをし尿や雑排水と一括して処理する方式は、最近米国などで普及しつつあり、ユーザーから見れば確かに手間の省ける魅力的な方式である。
しかし浄化槽への負荷が大きくなり、余剰汚泥の発生量も当然増える上に、万一トラブルが発生した場合には、ユーザーにはまったく手に負えない事態となる。
やはり、生ゴミは生ゴミ単独で処理する方式が、廃棄物処理上のセキュリティの面でも望ましいと言えるであろう。
以上のように見てくると、家庭用・業務用生ゴミ処理機の開発は、社会的意義の非常に大きなものであり、単なるブームに終わらないだけの必然性を備えていると考えられる。
農水省が「食品廃棄物再商品化法案(仮称)」を国会に提出する方針を固めたことが、最近報道された。
これは、外食産業や食品メーカーが出す生ゴミや残飯のリサイクルを促進しようとするもので、一定割合以上の生ゴミを肥料や家畜飼料にするよう義務づけることを目指している。
したがって、家庭用だけでなく、今後、やや大型の、業務用の生ゴミ処理機の需要も高まっていくであろう。
ただし後述するが、やや専門的な装置工学的に見た場合、特に小型の生ゴミ処理装置は、設計・操作の上で種々の難しい課題を抱えた、なかなかの難物である。
食品リサイクル法の概要(要旨)
国では西暦2000年を「循環型社会元年」と位置付けており、廃棄物の削減・再利用のための基本理念を示した「循環型社会形成推進基本法」及び基本法の理念に沿って各省庁が個別の廃棄物処理方法を、制定し、5月末迄に全ての法案が国会にて可決成立された。
この内、農林水産省は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」を制定。
平成12年6月7日交付。平成13年4月施行予定である。
食品リサイクル法
1.目 的
食品関連産業における食品廃棄物の排出量削減と飼料、肥料等の原材料としての再利用促進。
◎食品リサイクル法と「リサイクル」という言葉がでてくるが、法律の意図は「最終処分場対策」に重点が置かれており、他のリサイクル法とは若干趣旨が異なる法律。
2.責 務
(1)一般事業者及び消費者の責務
食品の購入又は調理方法の改善により食品廃棄物等の発生抑制に務めるとともに再生利用により得られた製品の利用等に務めること。
(2)国の責務
再生利用等を促進するため、必要な資金の確保とともに、情報の収集活用や研究開発の推進その他必要な措置を講じるよう務めること。
教育活動、広報活動を通じて国民の理解と協力を求めるように務めること。
(3)地方公共団体の責務
区域の経済的社会的諸条件に応じて再生利用等を促進するよう務めること。
3.法律対象(100万事業者程度と推計)
(1)食品の製造、加工、卸売、又は小売を業として行う者・食料品製造業者及び飲料製造業者(酒類製造業者を含む)
・飲食料品卸売り業者 ・小売業者
・百貨店 ・総合スーパー ・コンビニ等
(2)飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるもの
・飲食店業
・旅館 ・ホテル等
◎家庭系の食品廃棄物については現在適用を検討中である。
4.勧告・命令対象要件
年間排出量が100トン以上の事業者に対して「勧告→公表→命令→罰則(50万以下の罰金)」検討中(16000事業者・食品関連事業者の全体の1.6%)
[根拠]
1)再生利用を実施する場合のコストがその処理ロットからみて、一般廃棄物の委託処理費用と大差ない水準となること。
2)当該要件に該当する全事業者の排出量が、食品廃棄物の全体量の過半を超える。
5.事業者における取り組み目標
事業者は発生量の抑制・減量・再生利用の3手法を用い(優先順位なし)5年程度の目標年度までに食品廃棄物発生量の20%減量が目標。現在既に2割以上を再生利用等を達成している事業者は、今と同等以上の再生利用等の実施を期待。
6.食品関連事業者に対する指導監督業務
主務大臣が行い、具体的には地方農政局と食糧事務所が連携して行う方向で検討されている。
7.法律の主務大臣
主務大臣は農林水産大臣・環境大臣・財務大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣・国土交通大臣。基本方針の策定や勧告・指導等については各大臣が連携して実施。
8.再生される肥飼料の安全性確保
主務大臣が定める「食品関連事業者の判断の基準」の中で、肥料・飼料等の安全性の確保、品質の安定等を図ることを定める。また、基準の実施を指導・助言・勧告等により確保。
9.再生利用される肥飼料等の需要確保
再生利用の目標は、技術的および経済的に可能な範囲で需要に見合うものとなるように定める。
肥飼料の安全性・品質及び供給の安定性を「判断の基準」として定め、その実施を指導等により確保。
再生利用事業者の登録・再生利用事業計画の認定制度により再生利用製品の安全性を確保。
10.法案の骨子
(1)主務大臣は食品循環資源の再生利用等の促進の基本方向・再生利用等を実施すべき量に関する目標等について基本方針を定める。
(2)主務大臣は取り組むべき措置について、食品産業関連事業者の判断基準を定める。
また、これに基づき指導・助言、及び勧告・命令をすることが出来る。
(3)食品循環資源の再生利用を促進するため、これを原材料とする肥料・飼料等の製造を業として行う者は、登録再生利用事業者として主務大臣の登録を受けることが出来る。
(4)食品関連事業者・農林漁業等及び肥料・飼料等の連携を促進するため、3者が共同して、再生利用事業計画を作成し主務大臣の登録を受けることが出来る。(認定事業者)
(5)3・4で登録又は認定を受けた事業者に対し、廃棄物処理法、肥料取締法及び飼料安全性法に関する特別措置を講じる。
(6)主務大臣は食品関連事業者、認定事業者、登録再生事業者に対して、報告させ、職員に事務所、工場、事業所に立ち入り、帳簿、書類を検査させることが出来る。
(7)主務大臣は再生利用等が判断基準に照らして著しく不十分であると認めたときは、食品関連事業者に対して勧告・公表・命令を行うことが出来る。
11.法律の制定日
公布日から起算して1年程度後の期日から実施する。
ダイオキシン類排出削減及び廃棄物の適正処理の観点から平成13年4月1日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の施行規則の一部が改正され、平成14年12月1日から廃棄物焼却炉の構造基準が強化されます。
ダイオキシン類対策特別措置法(H12年1月15日施行)
1、火床面積0.5平方メートル以上もしくは、焼却能力50kg/hの炉を設置(使用)する場合、「ダイオキシン類対策特別措置法」に従う。
・都道府県知事へ提出
・年1回以上ダイオキシン類の排出値及び報告
(一般的に測定費用は、一回50万円以上かかる)
・測定値が基準を上回った場合、焼却設置の改善が必要。
つまり火床面積0.5L未満、焼却能力50kg/h未満の焼却炉は、対象外です。
新構造基準では(改正廃棄物処理法、H14年12月1日施行)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正(H14年12月1日施行)により、家庭用焼却炉を含め、すべての規模の焼却炉に対して構造的な新基準が定められる。
それによると以下のすべての条件を満たしていない焼却炉での使用は不可となる。
「構造基準の条件」(火床面積0.5L未満、焼却能力50kg/h未満の焼却炉でも対象になります。)
・空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却炉設備内と外気が接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われること。
・外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することが出来ること。(二重扉の設置など)
・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置(温度計)が設けられていること。(温度測定器の設置)
・燃焼ガスの温度を高温に保つことができるよう、助燃装置が設けられていること。
~適合しない焼却炉を使用した場合の罰則~
構造基準(廃棄物処理法第16条の2に規定する処理基準に含まれる基準)に適合しない廃棄物焼却炉設備での焼却行為は廃棄物の野焼きとなり、懲役3年以下若しくは、300万円以下の罰金またはその併科に処せられます。
- 行政対応 -
事業系生ゴミ処理機の助成金
食品リサイクル法などの整備により、ゴミの削減が騒がれている。各地方自治体では、事業者から排出される生ゴミの処理を支援し、減量化・資源化の促進を図るため、事業系生ゴミ処理機を購入する場合に、助成金を交付する。
事業系生ゴミ処理機助成額
| 都道府県 | 市町村 | 上限 | 支給率 | 備考 | 施行・更新日 |
| 栃木県 | 益子市 | 10万 | 1/2 | 過去実績1台 | |
| 埼玉県 | 久喜市 | 250万 | 1/2 | 過去実績1台 | 久喜宮代 衛生組合 |
| 宮代町 | 250万 | 1/2 | |||
| 川越市 | 100万 | 1/3 | 過去実績3台 | ||
| 東京都 | 小平市 | 30万 | 1/2 | ||
| 小金井市 | 30万 | 1/2 | |||
| 武蔵村山市 | 100万 | 1/2 | |||
| 調布市 | 50万 | 1/3 | |||
| 神奈川県 | 座間市 | 全額 | 集合住宅のみ | 2010.5.1 | |
| 横須賀市 | 20万 | ||||
| 秦野市 | 200万 | 3/5 | 20世帯以上で構成する団体 | ||
| 逗子市 | 2/3 | 集合住宅1世帯当たり 3万を上限 |
|||
| 新潟県 | 十日町市 | 100万 | 1/3 | ||
| 津南町 | 10万 | 1/3 | |||
| 富山県 | 高岡市 | 100万 | 1/2 | 100万or利用世帯×25000円 の低い方 |
|
| 石川県 | 輪島市 | 50万 | 1/2 | ||
| 能登町 | 20万 | 1/3 | |||
| 福井県 | 勝山市 | 400万 | 2/3 | ||
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 150万 | 1/3 | ||
| 鳴沢村 | 300万 | 80% | 当社実績13台、他社2台 | ||
| 長野県 | 安曇野市 | 10万 | 1/2 | ||
| 軽井沢町 | 5万 | 1/2 | |||
| 小谷村 | 100万 | 1/2 | |||
| 静岡県 | 熱海市 | 500万 | 1/2 | ||
| 御殿場市 | 500万 | 1/2 | |||
| 沼津市 | 200万 | 1/3 | 当社実績1台 | ||
| 富士市 | 200万 | 1/2 | 集合住宅・市内事業者 | ||
| 裾野市 | 100万 | 1/3 | 当社実績5台 | ||
| 川根本町 | 60万 | 1/2 | |||
| 愛知県 | 江南市 | 100万 | 60% | ||
| 岐阜県 | 高山市 | 100万 | 1/3 | ||
| 守山市 | 50万 | 1/5 | |||
| 三重県 | 鳥羽市 | 200万 | 2/3 | ||
| 伊勢市 | 3万 | 1/2 | 事業法人 可 | ||
| 和歌山県 | 新宮市 | 100万 | 1/3 | ||
| みなべ町 | 10万 | 1/3 | |||
| 島根県 | 松江市 | 100万 | 1/3 | ||
| 鳥取県 | 南部町 | 100万 | 1/2 | ||
| 鹿児島県 | 指宿市 | 200万 | 40% | 2014年度まで |
月刊廃棄物2012年7月
主要都市を対象に2011年11月に本誌が実施したアンケート結果に一部ホームページの情報を追加したもの。
※事業系可燃ゴミを自己搬入した場合の料金。比較のため、10kg、100kgごとの場合も1kg当たりに換算した。
| 都道府県 | 都市 | 1kg/円 | 施行・更新日 | 都道府県 | 都市 | 1kg/円 | 施行・更新日 | |
| 北海道 | 苫小牧市 | 14 | 2013.7.1 | 長野県 | 須坂市 | 15 | 2013年現在 | |
| 恵庭市 | 9.9 | 2013.4.1 | 諏訪市 | 15 | 2013.4.1 | |||
| 網走市 | 8 | 2013.4.1 | 長野市 | 13 | 2011.4.1 | |||
| 函館市 | 3.36 | 2013.4.現在 | 山梨県 | 甲府市 | 16.59 | 2012.2.23 | ||
| 札幌市 | 20 | 2013.1.1 | 岐阜県 | 恵那市 | 5 | 2012.4.11 | ||
| 帯広市 | 16 | 2012.11.1 | 岐阜市 | 11 | 2012.2.24 | |||
| 北見市 | 9 | 2011.4.1 | 静岡県 | 湖西市 | 12 | 2013.4.1 | ||
| 稚内市 | 5.5 | 2009.4.1 | 浜松市 | 12 | 2013.4.1 | |||
| 旭川市 | 7.5 | 長泉町 | 7 | 2011.4.1 | ||||
| 青森県 | 八戸市 | 9 | 2013.4.1 | 静岡市 | 10.5 | 2009.4.1 | ||
| 青森市 | 10 | 2013.2.12 | 愛知県 | 小牧市 | 20 | 2013.6.10 | ||
| 秋田県 | 秋田市 | 11.2 | 2008.4.1 | 岡崎市 | 10 | 2011.4.1 | ||
| 岩手県 | 釜石市 | 20 | 2009.4.1 | 田原市 | 10 | 2007.4.1 | ||
| 盛岡市 | 10 | 名古屋市 | 20 | 2006.2.17 | ||||
| 山形県 | 山形市 | 10 | 豊田市 | 10 | 2000.7.23 | |||
| 宮城県 | 仙台市 | 10 | 2012.6.1 | 豊橋市 | 10 | |||
| 福島県 | いわき市 | 10 | 2013.3.22 | 三重県 | 四日市市 | 15 | 2013年現在 | |
| 福島市 | 10 | 津市 | 15 | |||||
| 郡山市 | 10.5 | 滋賀県 | 大津市 | 15 | ||||
| 茨城県 | つくば市 | 18 | 2013.4.24 | 京都府 | 京都市 | 8 | 2006.4.1 | |
| 守谷市 | 21 | 2013.2.1 | 奈良県 | 橿原市 | 13 | 2013.4.2 | ||
| 水戸市 | 13 | 桜井市 | 16 | 2009.4.1 | ||||
| 栃木県 | 鹿沼市 | 22 | 2013.6.11 | 奈良市 | 10 | |||
| 那須町 | 5 | 2013.4.1 | 和歌山県 | 有田川町 | 10 | 2011.7.15 | ||
| 那須塩原市 | 10 | 2013.1.11 | 和歌山市 | 10 | ||||
| 宇都宮市 | 21.6 | 大阪府 | 枚方市 | 7.5 | 2015.12.31まで | |||
| 群馬県 | 前橋市 | 18 | 2013.3.12 | 堺市 | 11 | 2013.6.9 | ||
| 伊勢崎市 | 20 | 2013.2.13 | 島本町 | 15 | 2012.4.1 | |||
| 高崎市 | 15 | 豊中市 | 8.7 | 2012.4.現在 | ||||
| 埼玉県 | 入間市 | 15 | 2013年現在 | 東大阪市 | 9 | 2012.3.9 | ||
| 坂戸市 | 23 | 2013.6.11 | 和泉市 | 15 | 2009.7.1 | |||
| 所沢市 | 20 | 2013.5.7 | 高石市 | 15 | 2009.7.1 | |||
| 川越市 | 17 | 2013.4.1 | 大阪市 | 5.8 | ||||
| さいたま市 | 17 | 2013.3.1 | 高槻市 | 8 | ||||
| 川口市 | 15 | 2012.12.1 | 兵庫県 | 神戸市 | 8 | 2013.4.1 | ||
| 行田市 | 15 | 2012.8.23 | 西宮市 | 9 | 2009.8.7 | |||
| 蕨市 | 17.85 | 2011年現在 | 姫路市 | 10 | ||||
| 戸田市 | 17.85 | 2011年現在 | 尼崎市 | 10.3 | ||||
| 狭山市 | 17 | 2011.11.7 | 鳥取県 | 鳥取市 | 12 | 2006.4.1 | ||
| 千葉県 | 君津市 | 15 | 2013.7.1 | 島根県 | 松江市 | 15 | ||
| 市原市 | 20 | 2013.6.17 | 岡山県 | 岡山市 | 13 | 2004.4.1 | ||
| 浦安市 | 21 | 2013.5.28 | 倉敷市 | 13 | ||||
| 市川市 | 21 | 2013.4.26 | 広島県 | 広島市 | 6.9 | |||
| 千葉市 | 36 | 2013.4.11 | 福山市 | 15 | ||||
| 八千代市 | 22.05 | 2013.4.1 | 山口県 | 山口市 | 5.25 | 2012.12.6 | ||
| 柏市 | 18.9 | 2013.2.12 | 下関市 | 5 | 2009.4.1 | |||
| 船橋市 | 20 | 徳島県 | 徳島市 | 10 | 2008.4.1 | |||
| 東京都 | 23区 | 15.5 | 2013.10.1 | 香川県 | 高松市 | 15.5 | 2012.4.1 | |
| 調布市 | 35 | 2013.4.1 | 坂出市 | 20 | 2011.2.1 | |||
| 三鷹市 | 50 | 2013.4.1 | 愛媛県 | 四国中央市 | 7 | 2013.3.1 | ||
| 府中市 | 42 | 2010.5.1 | 松山市 | 12 | ||||
| 神奈川県 | 厚木市 | 25 | 2013.4.1 | 高知県 | 高知市 | 12 | 2010.12.16 | |
| 愛川町 | 25 | 2013.4.1 | 福岡県 | 福岡市 | 14 | 2013.4.1 | ||
| 川崎市 | 12 | 2013.3.20 | 久留米市 | 15 | 2009.11.20 | |||
| 伊勢原市 | 19 | 2010年現在 | 北九州市 | 10 | ||||
| 横須賀市 | 15 | 2009.11.4 | 熊本県 | 熊本市 | 12 | |||
| 横浜市 | 13 | 大分県 | 大分市 | 8 | 2012.5.現在 | |||
| 相模原市 | 18 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3.15 | ||||
| 新潟県 | 新潟市 | 13 | 2007.6.1 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7 | ||
| 富山県 | 高岡市 | 12 | 2013.3.21 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6 | ||
| 富山市 | 18 | 長崎県 | 長崎市 | 6 | 2013.3.1 | |||
| 石川県 | 金沢市 | 8.4 | 沖縄県 | 那覇市 | 9 | |||
| 福井県 | 福井市 | 4.2 |
- 参考文献 -
はじめに「はじめに-生ゴミ処理装置開発の意義-」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。 最近、各種の生ゴミ処理機が多数開発されるようになった。
その背景にはゴミ問題の深刻化がある。家庭・オフィスなどから排出される一般廃棄物は、90年代を通じてほぼ年間5000万トンで推移している。
一般廃棄物はリサイクル率が約1割と低く、大半が焼却されている。
その焼却灰を埋め立てる最終処分場の枯渇が現実の問題になってきたことと、
焼却に伴って発生するダイオキシンが問題となって、焼却すべきゴミの量そのものを減らす必要が以前よりさらに強まった。
一般廃棄物の大部分は可燃ゴミであり、可燃ゴミの約4割が生ゴミと言われている。
したがって、生ゴミを一般廃棄物から除去できれば、それだけで焼却すべきゴミの量がかなり減少する。
生ゴミ中の塩分はダイオキシン発生の一因でもあるから、この面でも生ゴミの隔離には意味がある。さらに、一般廃棄物に生ゴミを混入させなければ、残りは紙・繊維・プラスチック・ガラス・金属等であるから、悪臭やハエ等の発生もなく、機械的分別による再資源化の可能性が高まる。
焼却処分する場合にも、廃棄物中の水分が減少して効率的な熱回収が行える。
こうして見ると、一般廃棄物中に生ゴミを混入させないことによるメリットは、極めて大きい。
たとえ生ゴミをコンポスト化して土壌還元することが可能でない場合にも、発生源で生ゴミを処理することの意義は大きい。この点は大いに強調したい。
生ゴミは腐敗しやすく悪臭も放ちやすいので、輸送や集積が難しい。しかも発生源が分散している。当然、各発生源での個別処理が望ましい。
ディスポーザーを用いて生ゴミをし尿や雑排水と一括して処理する方式は、最近米国などで普及しつつあり、ユーザーから見れば確かに手間の省ける魅力的な方式である。
しかし浄化槽への負荷が大きくなり、余剰汚泥の発生量も当然増える上に、万一トラブルが発生した場合には、ユーザーには、まったく手に負えない事態となる。
やはり、生ゴミは生ゴミ単独で処理する方式が、廃棄物処理上のセキュリティの面でも望ましいと言えるであろう。
以上のように見てくると、家庭用・業務用生ゴミ処理機の開発は、社会的意義の非常に大きなものであり、単なるブームに終わらないだけの必然性を備えていると考えられる。
農水省が「食品廃棄物再商品化法案(仮称)」を国会に提出する方針を固めたことが、最近報道された。これは、外食産業や食品メーカーが出す生ゴミや残飯のリサイクルを促進しようとするもので、一定割合以上の生ゴミを肥料や家畜飼料にするよう義務づけることを目指している。
したがって、家庭用だけでなく、今後、やや大型の、業務用の生ゴミ処理機の需要も高まって行くであろう。ただし後述するが、やや専門的な装置工学的に見た場合、特に小型の生ゴミ処理装置は、設計・操作の上で種々の難しい課題を抱えた、なかなかの難物である。
処理方式「生ゴミ処理方式の分類と処理特性」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。大別して、生物処理方式と物理化学的処理方式があるが、細分すると次のようになる。
| 1) | 微生物分解型 | 微生物の代謝能力を利用して生ゴミ中の有機物を水と炭酸ガスに 酸化分解するもの。バイオ型、生分解型などとも呼ばれる。 |
| 2) | コンポスト型 | 基本的には前者と同様であるが、 ゴミの減量よりもコンポスト(堆肥)の生成を主な目的とするもの。 |
| 3) | 乾燥型 | 電熱・温風・マイクロ波などを利用して生ゴミ中の水分・揮発分を 蒸発させ、乾燥・減量を図るもの。 |
| 4) | 炭化型 | 電熱恨風・マイクロ波などを利用して、乾燥型よりさらに高温状態を 作りだし、生ゴミを炭化させるもの。 |
この他にも物理化学的処理方式としては、焼却・冷却・脱水などがあるが詳細は略す。
上記のうち 1)と2)が生物処理方式、3)と4)が物理化学的処理方式である。
家庭用の生ゴミ処理機では、1)のバイオ型と3)の乾燥型が人気を二分している。
業務用では大半が生物処理方式である。
(物理化学的処理方式ではエネルギーコストが過大)
乾燥型の主流は温風乾燥式で、130℃程度の温風で生ゴミを乾燥させる。
家族4人の標準的排出量700g/日の生ゴミに対して、処理時間は2時間半ほどで、重量は約1/5、容量は約1/7になるといったタイプが多い。
基本的に有機物の分解は行わないので、週に1度程度の乾燥生ゴミの取出しが必要となる。
乾燥型は一般にコンパクトで、密封性が高い装置であれば室内にも設置可能、かつ操作が簡単で処理時間が短いという長所がある半面、電熱を利用するため電気代がかさみ、本体価格もバイオ型より高めになる。
炭化型ではその傾向がさらに顕著であり、コストの高い処理方式となるため、少なくとも家庭用としては一般的でない。
一方、家庭用生ゴミ処理機市場の約6割を占めると言われているのが、生物処理方式、特にバイオ型の処理装置である自然界には多種多様な微生物群が存在し、動植物の遺体や残渣を分解・浄化して炭素をはじめとする地球上の各種元素の循環を進める重要な役割を果たしている。
これらの微生物群の中から特別な働きを持つものを選び出して利用するのが、微生物利用技術である。
生ゴミに限らず一般に有機質廃棄物の処理には、この微生物利用技術が応用される例が多い。それは、焼却・吸着その他の物理化学的処理に比べて、この技術が穏和な操作条件・簡易なプロセス・安いコスト等の有利な面を持つ場合が多いからである。
順理的に自然界での微生物の活動を応用するため、地球環境へのインパクトも本来少なく、「環境に優しい技術」と言ってよい。
しかし一方、微生物を利用すること自体に由来する制約も存在する。
各種の操作条件は、微生物の活躍できる範囲に限定されるし、処理の対象も、微生物の処理能力による制限を受ける。
また、医薬品の生産などと異なり、特に廃棄物処理の分野では、単一種の微生物が用いられることは稀で、複数種の微生物が共存する条件下でうまくバランスを 取りながら、それらの機能を発揮させることが求められる。
反応の速度自体も、物理化学的処理に比べて遅い場合が多い。
したがって、生ゴミ処理においても微生物利用方式を選択するかどうかは、その処理技術についての十分な基礎知識を修めた上で、他の選択肢との技術的・経済的な得失を慎重に比較・検討して決めなければならない。
| 処理方法 | 環境負荷 | 減量率 | 装置費 | 運転費 | 使い易さ | 安全性 | 総合評価 |
| 微生物 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| ディスポーザ | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 21 |
| 乾燥 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 脱水 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 焼却 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 冷却 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 |
なお筆者自身は、生ゴミ処理においては微生物処理方式を第一選択肢と考えている。その根拠となる各方式の比較評価の一例として、参考までに各処理方式に対する定性的な評価の例を表1に示す。
この表では、いくつかの評価指標(ランニングコストや環境負荷など)を筆者の判断で5段階評価し、その合計点の高い順に並べてある。
表に見られるように生ゴミ処理においては、種々の側面から判断した場合に、微生物利用型の処理が望ましいことが示唆される。以下、本稿では微生物処理方式を前提として、装置の解説等を試みたい。
分解の原理「生ゴミ分解の原理」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。 生ゴミの分解過程を図示すると図1のようになる。
糖・でんぷん質・脂肪やたんぱく質など微生物の栄養源となりやすい成分は、比較的すみやかに分解され、セルロース(繊維質)などは長期間未分解のままで残る。
微生物処理方式の場合、生ゴミ中の有機物に含まれる炭素・酸素・水素の大半は、炭酸ガスと水になって装置外に排出される。
一部は微生物の体内に取り込まれ、菌体として残る。(微生物は増殖と死滅を繰り返しているので、菌体だけが増え続けることはない)。
またタンパク質などに含まれる窒素は、大半が無機化されてアンモニウム感または硝酸態の窒素となる。内部のpHなどによってはアンモニアガスとして排出されることもあるが、相当部分はアンモニウム態または硝酸態窒素の形で残留する。
生ゴミ中の無機物は、分解・気化されることはなく、そのまま残留する。
図中、灰分と呼ばれる部分である。燃焼させても灰は残ることで理解できる。
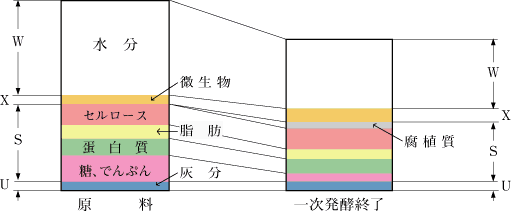
図1 生ゴミの分解過程の模式図
乾燥型の主流は温風乾燥式で、130℃程度の温風で生ゴミを乾燥させる。
家族4人の標準的排出量700g/日の生ゴミに対して、処理時間は2時間半ほどで、重量は約1/5、容量は約1/7になるといったタイプが多い。
基本的に有機物の分解は行わないので、週に1度程度の乾燥生ゴミの取出しが必要となる。
乾燥型は一般にコンパクトで、密封性が高い装置であれば室内にも設置可能、かつ操作が簡単で処理時間が短いという長所がある半面、電熱を利用するため電気代がかさみ、本体価格もバイオ型より高めになる。
炭化型ではその傾向がさらに顕著であり、コストの高い処理方式となるため、少なくとも家庭用としては一般的でない。
生ゴミを微生物処理させると、次第に黒土のような性状を呈するようになる。
この中には、低分子化された有機物や難分解性有機物などが残存しており、腐植質と呼ばれる。
これらは生物分解が困難な物質に属し、生ゴミ中の有機物といえども100%分解させることは困難である。
現在生ゴミ処理機の主流となっている生分解型(消滅型とも呼ばれる)の場合には、コンポスト型よりも有機物の分解率をできるだけ高める操作を行うが、それでも「完全消滅」はあり得ない。
メーカーの中には「完全消滅」を売り物にしたり、極端な場合には「元素にまで分解」などと宣伝するケースも見られるが、これは微生物の代謝を利用する限り原理的にあり得ない、全く非科学的な主張である。
生ゴミの減量率について、簡単な計算例を以下に示す。
含水準70%の生ゴミ1kgがあるとすると、水分が700g、乾物が300gあることになる。乾物の1割を無機物とすると、これが30gある。
これはそのまま残留する。残る有機物(270g)の85%が分解できたとすると、残留する有機物は270×0.15=40gになる(生成する菌体量も考えると、見掛け上の有機物分解率はこの程度にみておく方が安全であろう)。
したがって残留する乾物は合計70gとなり、残渣が含水率30%で排出されるとすれば、残渣の重量は、ちょうど100gとなる。すなわちこの場合、投入した生ゴミの重量(湿重量)の減少率は90%ということになる。
有機物の分解率85%、残渣の含水準30%としてもこの程度の値である。
言い換えれば、投入した生ゴミの9割が消滅すれば、微生物分解が比較的順調に進行している証拠と考えてよい。
装置の分類「処理装置の分類と特徴」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。 現在、生ゴミ処理装置には様々なものが考案され、出願されている特許件数も膨大な数にのぼる。
それらをすべて網羅し分類することは不可能に近い。
ここでは、装置工学的な観点からごく概略の分類を試みる。
生ゴミ処理装置の分類指標としては、操作温度、撹拝方式、通気方式、バルキング材の有無とその種類などが挙げられる。
操作温度
大別して高温型(60℃前後)と中温型(30~40℃)に分けられる。
下水汚泥のコンポスト化操作などでは高温での操作が反応速度を高く保つ上で有利になるが、生ゴミ処理の場合は、分解しやすいためか、中温での操作でも実用上、分解速度の違いはさほど感じられない。
高温操作の場合には、加温に必要なヒーターの消費電力が大きくなり、また一般に高温の方が強い臭気を発生するケースが多く、
家庭用の生ゴミ処理機では中温操作が一般的である。中には加熱を行わず、温度維持は発酵熱の発生のみに頼ってあとは室温放置、という方式もある。
寒冷地以外ではこの方式でも比較的順調に操作できる場合がある。
生ゴミ処理では、比較的低い温度でも分解が進むケースが多い。
なお通常の微生物では、好熱性と呼ばれる菌群でも最適生育温度は60℃前後で、70℃以上の高温では微生物の活性は急速に低下する。これは菌体を構成するタンパク質の変性温度が60℃前後だからで、低温殺菌(パスツーリゼーション)が60℃付近を基準とするのもこの理由による。
したがって80℃とか85℃での微生物処理をうたうメーカーや装置も存在するが、極めて特殊な微生物を用いた例と考えられる。
撹拌方式
撹拌は微生物と生ゴミの接触を促し、かつ新鮮な空気を取り入れ内容物の均一化を図るために必要な操作で、ほとんどの処理装置が何らかの撹拌機を採用している。
圧倒的に多いのは、回転軸を横に通し適当な形状の羽根を固定させて内容物をかき混ぜる方式である。
撹拌羽根の形状は各社さまざまであり、羽根ではなく棒を用いるタイプもある。回転軸が縦になる方式は、1点支持型になると槽底部を貫通させる場合には、シールが問題になるなどの理由で、実用例は多くない。
また上記のような内部撹拌ではなく、槽全体を回転・振動・上下動などさせることにより内容物の混合を図る方式も考案されているが、実用例は未だ少ない。
撹拌の最適条件を求めることは、実はかなり難しい。
まず撹拌の強度(毎分の回転数)をどのようにとり、連続撹拌するか間欠撹拌にするかを決めなければならない。
撹拌を行わないと内容物の均一化が阻害され、空気の流通が滞って分解速度が低下するから、ある程度の撹拌が必要ではあるが、消費電力を節約する意味からは、撹拌をなるべく省きたい。
通常は、タイマーなどを用いた間欠撹拌が採用されることになるが、撹拌のON/OFFの長さと比率の組み合わせは無限にあるから、実験ですべての条件を試すことはできない。
したがって多くの場合、撹拌条件は経験的に決められている。
バルキング材
多くの生ゴミ処理機では、通気を促すため堆積層内に粒状の副原料を混合する。
この副原料はバルキング材と呼ばれ、オガクズ・モミガラなどのほか、ウッドチップも用いられる。その働きは反応・進行に必要な酸素を供給するための空間を堆積層内に作るだけでなく、水分調整材としての役割も果たす。
したがってバルキング材の必要量あるいは最適使用量は、通気性改良材としての働きと水分調整材としての必要性の両面から決められることになる。
現在、最も多く使われているのはオガクズである。ウッドチップは分解速度が小さいので、残渣を篩い分けしてリサイクル使用できる。
原料へ混合したウッドチップの約70%が回収・再利用されるといわれている。
オガクズは家畜舎の敷料にも用いられ、畜糞尿の水分を吸収して廃水処理を不要とする利点があるため、需要が多い。地域によっては1万円/m3以上もする場合があり、生ゴミ処理の経済性に大きな影響を与える。
一方、モミガラはオガクズに比して用途の競合が少ないので入手は比較的容易であるが、排出時期が限られるという大きな欠点がある。
(嵩密度が小さいので、年間を通じて用いるには大きな貯蔵空間・敷地を要する)
モミガラはまた、そのままでは堅く吸水性が小さいため、しばしば破砕して用いられるがシリカが多く堅いため、破砕機の摩耗速度が大きく電力節約の意味からも、破砕の度合は最小限に留められている。
最近はバルキング材としてセラミックス粒子を用いる例なども現れている。
オガクズ・モミガラなどは一定期間ごとに交換・追加などを行わなければならないのに対し、こうした無機物ではかなりの長期間、交換不要で使える利点がある。
今後、使用に便利なバルキング材の開発が進むものと予想される。
通気方式
通気は反応に必要な酸素を供給するとともに、生ゴミ中の水分を系外へ排出し、槽内部温度の調節も行う重要な操作で、ほとんど全ての生ゴミ処理機にはブロワーまたはファンによる通気装置が装備されている。
ただし、通気は大半が堆積層上部から行われ、空気が堆積層表面をかすめていく方式であるため、通気の効率はさほど高くない。
理想的には、層底部から通気するのが効率的であるが、散気装置の目詰まり等の問題があり、底部からの通気方式は少ない。
また後述するが、通気量の制御は処理機の操作因子として極めて重要であるが、通気量の完壁な制御を実現した装置は未だ見当たらない。
性能指標「処理性能の指標」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。 生ゴミ処理機の「性能」とは、何を指すのだろうか?
コンポスト型の場合には、単にゴミの減量率ではなく、得られる製品コンポストの品質や収量なども評価の対象になるであろう。
消滅型の処理機の場合には、まずゴミの減量率が処理性能の基準となるべきであるが、現時点では統一化された基準で性能が提示されていない。
例えば、全国各地で開催される廃棄物処理展や環境フェアなどに展示される生ゴミ処理機の処理性能に関して、筆者の印象ではあいまいな表現で語られる場合が多いように感じられる。
いわく「無くなります」「消えます」「完全に消滅します」などなど。
しかし、実際に測定データが示されることは、ほとんどない。
説得力のあるデータをきちんと示す必要がある。
単に見かけ上、消えて無くなったように見えるだけではダメである。
大量のバルキング材に埋もれてしまえば、確かに消えて無くなったように見える。
特に分解が進むと容積の減少は顕著であるから、見た目にはよく分からなくなる。
しかし重量が減少していなければならない。重量基準の処理性能表示は必須である。
まず基準となるのは、生ゴミ全体の減量率である。先に簡単な計算例を示したこの「減量率」は、水分を含めた投入生ゴミ全体の変化量を表すものである。
この値を得る最も単純で直接的な方法は、処理機全体を秤に載せて、その重量を経時的に測定することである。
ただし、通常は生ゴミ処理構内にはオガクズなどのバルキング材も混在しているので、得られる値は、これらに含まれる水分の変化などすべてを総計したものである。
すなわち、短時間ではバルキング材自身の乾物重量は変化しないものとして、
全体の重量変化量=生ゴミの重量変化量+バルキング材の水分変化量(1)
と考えてよい。
この場合の「減量率」は、次式で得られる。
減量率=全体の重量変化量/生ゴミ投入量 (2)
この値は、1日当たりの値、あるいは処理開始からの累積値で求めることになる。
いずれにせよ、減量率の算出には処理槽内堆積物の平均含水率の測定は必須である。
1ヶ月といった連続処理実験の際には、時々減量率が100%を超える日も出てくる場合がある。
それは、堆積層内の水分減少量と有機物分解量が大きく、投入生ゴミ重量を超えてしまったケースである。累積値で見た減量挙が100%を超えるような場合には、バルキング材等の減量を疑う必要がある。
先の計算例で見たように、投入された生ゴミの重量減少率が90%を大幅に超えることは、滅多に起こらないからである。
上記の処理性能は、生ゴミ全体の重量基準であるが、生ゴミの「分解」を中心に考えるならば、乾物中の有機物を基準とした「減量率」を求めなければならない。
乾物中の有機物量は、通常「強熱減量」で表される。
この値は、有機物を乾燥させて重量を測定し、次に800℃以上の高温で燃やし(恒量に達した磁器坩堝[るつぼ]を用いる)、得られる灰分の重量を測定して、両者の差を取ることで得られる。
ただし実際には、生ゴミ処理槽内にはオガクズなどのバルキング材が混入している場合が多いので、投入前はともかく、槽内に投入された生ゴミ中の有機物だけを正確に測定することは難しい。
残渣とバルキング材が簡単に分離できるような装置であれば、上に述べた方法で強熱減量を計測し、有機物の分解率を正確に求めることができる。
消滅型の生ゴミ処理機の性能としては、重量の減少率が重要であることは論を待たないが、その他にも次のような幾つかの指標が考えられる。
1)臭気発生の少なさ(実際の使用に当たっては極めて重要)
2)維持管理の容易さ(同上)
3)エネルギー消費の少なさ
4)残渣の取りだし、または内容物の交換の容易さ
5)使用上の清潔感
6)静粛性(実際の使用に当たっては案外重要)
7)長期的な性能の安定性
8)装置自体の耐久性
9)経済性(装置・設備自体のコストとランニングコスト)
10)コンパクト性(大きすぎる装置は邪魔である)
これらの中には、数値化が容易なものと困難なものがあり、また計測の容易でないものが多いが、いずれも実際の使用に当たって、ユーザー側から当然求められる性能であり指標であろう。
こうして見ると、生ゴミ処理機に求められる技術的課題の多さが改めて浮き彫りになる。
操作条件「操作条件について」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。植菌の効果
生ゴミ中の有機物分解の主役を担っている微生物は、決して特殊な微生物ではない。
与えられた条件下で自然に増殖してくる微生物と考えてよい。
通常生ゴミ処理機では、特に植菌を行わなくとも、2~3日もすれば分解に必要な微生物は増殖してくる。その様子を示したのが図2である。
これは筆者の実験室で、何も微生物を植菌しない静置型の生ゴミ分解実験を30℃で行った場合の、微生物数の経時変化を表したものである。
図の縦軸の単位は、試料の乾物1g当り、何個の微生物がいるかを表す数字である。
なお、縦軸は対数目盛りとなっている点に注意されたい。
図から明らかなように、微生物の数は、最初10の7乗程度であったものが、
3日目頃には10の11乗近くに達している。すなわち1万倍にも増えたことになる。
図にプロットが2種あるのは、2回の実験を行ったからである。
図より、実験の再現性はよくとれていることが分かる。
こうした実験を重ねることから、次のような諸事実が明らかにされている。
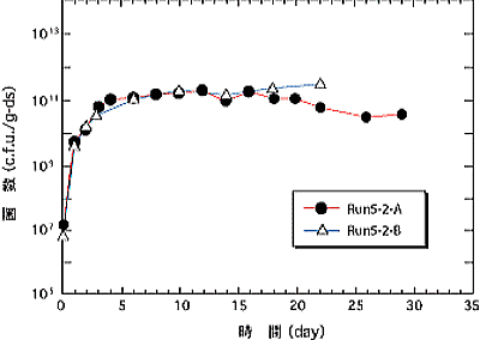
図2 生ゴミ分解過程における微生物数の経時変化
・植菌しなくても、条件が整っていれば微生物は2~3日で1万倍近く増える。
・その後は微生物数が飽和して(つまり上限に達して)、数は増えなくなる。
・優占微生物の種類は限られていて、せいぜい数種類である。
・人工的に後から加えた微生物が、そのまま1万倍近く増えて優占株となるケースは、きわめて稀である。
含水率とpHの影響
有機物の酸化分解反応が活発に進行するためには、好気的な条件が維持されなければならないが、そのためには、堆積層内の水分がある限界値以下に保たれなければならない。
この水分の限界値は、固体粒子間の接点に水がしみ出してくるときの含水率と考えてよい。この値は原料固体の性状、特にその親水性や粒度によって左右される。
安定な反応の進行のためには、初期含水準を65%程度以下に保つことが望ましい。原料の含水準がこれよりも高い場合には、乾燥した水分調整用材料(前述のバルキング材:オガクズやモミガラが多い)または処理後の残渣の一部を返送し混合してやる必要がある。
もちろん、水分調整材・残渣の両者を併用する場合も多い。
微生物の生存と活動のために水の存在は欠かせないので、層内の水分が少なすぎても微生物は活性を失う。水分30%以下では、生ゴミ分解の反応速度は急速に低下する。
したがって、処理槽内の含水準は30~65%の範囲にあることが望ましいことになるが、筆者の経験では含水準は40%前後に維持する方が、臭気の発生が少なく、使用上の清潔感もあり、内容物の粘度が高まる「団子化」現象も起こりにくいようである。
生ゴミ処理に関与する微生物の活動にとって、固体のpHも重要な因子である。
通常、中性ないし弱酸・アルカリ性、すなわちpH6~8.5程度で、それらの微生物は活発に働く。生ゴミのような有機質廃棄物を嫌気条件下で放置すると、酸発酵とよばれる反応が進行して酢酸などの低級脂肪酸が蓄積し、pHが4~5付近まで低下する。
その結果、悪臭を放つだけでなく、分解反応そのものも阻害されてしまう。
このような場合には、反応の開始までに時間がかかる。また反応途中でpHがあまりにも低下してしまうと、分解が停止し、単にpHを引き上げるだけでは状態が改善されないケースが多い。
原料のpHがあまりに低い場合には、消石灰・炭酸カルシウム等を混合してpH調整を行う必要がある。前述したように、処理後の残渣と原料を混合するだけで、支障なく反応を開始させることができる場合もある。
普通の原料であれば、分解反応の進行に伴い、二酸化炭素の他にタンパク質の分解によってアンモニアも発生し、これらが固相のpHを自然に調整する働きをしてくれることもしばしば見られる。
槽内温度・通気
生ゴミ処理機の堆積層内温度は、原料有機物の酸化反応による発熱と、堆積層からの放熱のバランスにより決まる。
放熱の要素としては水分の蒸発熱、通気の昇温、堆積層からの熱伝導による熱損失などがある。
堆積層の体積が小さければ、層からの熱損失が大きくなる。
(そのため小型の生ゴミ処理装置は、自己発熱で温度を維持するのが難しくなる)。
大型の装置では、堆積層内に通気を行わないか、または通気量が少ない場合には、層内部の温度は70℃、時には80℃以上もの高温に達する。
しかし、70℃以上もの高温では、微生物の多くはその活性を急速に失ってしまう。
先に述べたように、下水汚泥等のコンポスト化の最適温度は55~65℃の範囲にあると考えてよいが、生ゴミ処理の場合には、30~40℃程度の中温領域でも十分な分解速度が得られる。
通常、最適温度を超えると微生物の活性は急速に低下するが、最適温度より低い温度領域での活性の低下は緩やかだからである。堆積層内を好気的に保ち、分解反応速度を高く維持するために層内の通気は欠かせないが、層内を好気的に保つことだけが目的であれば、必要な通気量は極めて僅かで済む。
例えば、層下部に通気管を設置しておけば、酸化反応による発熱で層内温度が上昇し、それによって生じる自然対流だけで十分な通気が行われる。
しかし、固相の水分を蒸散させ、層内温度を最適に保つことを目的とした場合には、微生物にとって必要な酸素供給量の10倍以上の通気量が必要となる。
この場合、自然対流では通気量が不足するので、通常、強制通気方式が採用される。
最適な通気の条件として、微生物活性を最大に保つ温度(前述の通り60℃前後が多い。ただし分解しやすい原料では、より低温でも可能)
を保つように流量を制御することが望ましい。
すなわちこの場合の通気は、微生物に酸素を供給するよりはむしろ、堆積層内の水分及び温度の制御手段である。具体的な通気量の目安としては、生ゴミ処理では20~200L/min/kg-投入生ゴミの範囲にあると考えてよい。
なお、この値は、外気温度・湿度、処理構内温度と排気の湿度等により変化する。
通気量の制御は、生ゴミ処理装置の最適運転の要である。水分の収支バランスから通気量を計算するときの考え方を、図3に示す。
この場合、水分収支は、
(入る水分=生ゴミ中の水分+空気中の水分)=(出る水分=排気中の水分)
と表すことができ、排気の温度は30℃で水蒸気で飽和しているとして、通気量Nは次式で求められる。
N=1/(31.824-H)X×XY/100 (3)
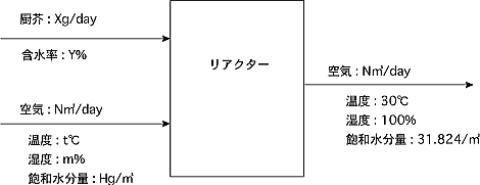
図3 生ゴミ処理機まわりの水分収支の考え方
式(3)から分かるように、投入した生ゴミ中の水分をとばすために必要な通気量は、生ゴミの量と含水量および通気される空気の温度・湿度によって変化する。
一例として、含水率75%の生ゴミ1kgの水分を1日でとばすための通気量を、入口空気の温度と湿度の関数として線図に表したものを図4に示す。
上に述べた通気量の目安、20~200L/min/kg-投入生ゴミが視覚的に理解されると思う。もちろん水分をもっと短時間でとばしたい場合には、通気量を増やし、撹拌も十分に行わなければならない。
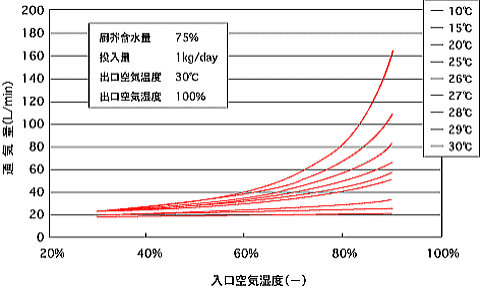
図4 入口空気の温度と湿度から通気量を求める線図
撹拌
微生物は固体粒子の内部には侵入し難いので、固体粒子の幾何学的な表面積の大きさもまた、反応速度を支配する重要な因子になる。
例えば汚泥などを粒状に成形すると、コンポスト化速度は非常に小さくなる。
堆積層の切返しは、層内での均一な発酵反応の進行を促し、新しい固体表面と菌体の接触の機会を増大させることにより、反応速度を高めるのに有効な役割を果たす。
また、通気を行わないときには、堆積層の切返しの頻度が層内の微生物への酸素供給速度を支配し反応速度を決定する。通気が十分な場合には、切返しは1日1~数回程度で十分な場合が多く、必ずしも機械的な連続撹拌が必要不可欠というわけではない。電力消費を節約するには、撹拌の強度や運転間隔を適当に調整しなければならないが、この条件は、先にも述べたように経験的に決められているケースが多い。
装置の制御
微生物反応による生ゴミ処理を円滑に進めるための操作因子としては、1)温度、2)含水準、3)通気量、4)pHなどが考えられる。
槽内温度は、槽加熱用ヒーターと槽温度及び外気温度センサーがあれば制御可能である。有機物分解反応が活発に進行する場合には、発酵熱の寄与も無視できないが、小型装置では放熱が大きいので冷却まで考える必要が生じるケースはまれで、単にヒーターを切るだけでよい。
難しいのは槽内含水率と通気量の制御である。
含水率が高い場合には、通気量を増やして水分の蒸発を促し、含水率が所定の値にまで低下したら通気量をしぼるか通気を停止しなければ、槽内は乾燥しすぎの状態に陥る。
これを制御するには、槽内の含水率を正確にモニターして、換気ファンの制御に連動させるのが最も直接的かつ効果的である。
排気中の湿度センサーを用いる方式を採る場合も見られるが、槽内の含水率と排気湿度が比例関係にないので、有効な方法とは言えない。
やはり、槽内含水率を直接的にモニターしたい。
この場合、センサーに求められる条件は、非接触的かつ非サンプリング的に含水率を検出できることであり、その方法をめぐって数多くの特許が申請されている。
筆者らもそうした水分センサーを開発している。
pHに関しては、非接触的に測定することは困難であることと、常時の監視は必要ないことから、小型装置ではモニターを考えないこととする。
生ゴミの重量変化を検出するのは、槽の重量を圧力センサーなどでモニターすれば可能であるし、そのような方式による特許出願例もある。
より直接的には、排気中の炭酸ガス濃度を検知すれば、有機物の分解速度を正確にモニターできる。
しかし実験装置ならばともかく、コスト的制約の厳しい小型生ゴミ処理機に搭載することは困難であろう。
臭気対策「臭気対策について」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。 生ゴミ処理装置における苦情で最も多いのは、悪臭の発生である。
生ゴミは腐敗しやすく、ほんのわずかな操作ミスでただちに悪臭が発生するからである。
脱臭対策としては、活性炭・その他吸着材を用いるのが最も簡易な方法であるが、湿度の高い排気を通じることや交換までの寿命が短いことなど、多くの弱点を抱えている。吸着剤に固体でなく液体を用いても、事態はさほど好転しない。
脱臭を本格的に考えるならば、何らかの酸化触媒を用いて、悪臭物質を酸化分解するのが最も早道であろう。
業務用の大型装置であれば、ガスを用いて燃焼させる手もあるが、家庭用では難しい。オゾン発生器を用いる方式は、分解できる悪臭物質が限定されることと、オゾン発生器の寿命が短いことが致命的な欠陥となっている。
結局、できるだけ低温で悪臭物質を酸化分解する以外にはなく、そのための触媒捜しが技術的課題と言える。筆者らが試用した酸化触媒では、最低350℃の温度が必要で、排気を昇温するヒーターが300W以上にもなることが判明して、使用を断念している。
より低温で分解が行える先触媒め使用も検討されている。
しかし家庭用の生ゴミ処理機では、必ずしも脱臭装置をつけなくとも操作可能なのではないかと、筆者は考えている。
これまでの経験では、操作が順調な場合には、臭気がさほど気にならない程度に抑えられることが多く、ベランダなどの屋外設置の場合には、十分実用に耐えるのではないかと考えるからである。
この場合、先に述べた装置の制御が大切で、しっかりしたモニタリングと的確な制御により安定した生ゴミ分解が行えるならば、特別な臭気対策が不要になると考えられ、その可能性は追究に値する。
諸問題「メンテナンス上の諸問題残渣の処理など」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。 多くの処理機では、バルキング材にオガクズなどを用いているため、残渣はバルキング材を含んだまま排出される。
当然、バルキング材の補給も必要になり、維持費がかさむ原因となっている。
また排出される残渣の含水率が高い場合には、臭気や不潔感が強くなり、ユーザーには好まれない。
含水率が低く、サラサラ状態でバルキング材と分離して排出できる方式が望ましい。
さらに、残渣の排出がワンタッチで、掃除機のバッグのように交換できる方式であれば、手も汚れず操作感も優れたものとなる。
装置そのものは、メンテナンス・フリーが望ましいことは言うまでもない。これを可能とするのは、結局、前述した装置の操作条件の徹底的に的確な制御である。
おわりに「おわりに-小型生ゴミ処理装置の困難と魅力-」
静岡大学工学部物質工学科 松田 智
本書は松田先生の了解の基に生ゴミ処理機ハンドブック(静岡県環境ビジネス協議会発行)より転記しております。 生ゴミ処理メーカーは、全国に200社以上も存在すると言われている。
市場に登場する生ゴミ処理機も数多く、出願されている特許数も万のオーダーに達する。
しかし現時点で、これこそ「決定版」と呼べる機器は、筆者の知るかぎり存在していない。求められる要件が数多くかつ厳しいからである。
大型装置ならば可能なことが、家庭用機器であるためにできないことも多い。
気固反応装置の一種として見た場合、小型生ゴミ処理装置は、設計・操作・制御、どの面から見ても一筋縄ではいかない難しい反応器である。
しかし冒頭で述べたように、その開発の意義は大きい。
今後、各メーカーが切瑳琢磨して、より性能の高い生ゴミ処理機が開発することが期待される。
